作業療法に役立つ臨床推論 ―高次脳機能障害の生活障害を分析する推論思考過程の理解―
電子版あり
定価:4,950円(本体4,500円+税)
商品コード: ISBN978-4-89590-757-6
内容紹介
生活障害の科学的分析に基づいたOT臨床推論の入門に最適の一冊!
リハビリテーション領域においても近年よく耳にするようになった臨床推論(クリニカルリーズニング)。作業療法士(OTR)は、対象者の多種多様な生活における困難さ、すなわち生活障害へ介入する医療専門職ですが、これら対象者は医学的要因と社会的要因が複雑に組み合わさった個別性の高い状況にあります。
これら対象者のうち、特に高次脳機能障害を抱える対象者に対して、その生活障害を分析し、統合と解釈を行い、介入するためには、確かな基礎知識と豊富な臨床経験が必要とされることは想像に難くないでしょう。
本書では、臨床推論(クリニカルリーズニング)の基本的な考え方から、分析の思考過程、統合と解釈、そして評価や介入といった、作業療法士ならではの推論思考過程を丁寧に解説しています。
臨床の場では、経験として語られることで終わってしまう場合が多いところもありますが、その臨床力を一つ一つ整理していくことで、科学的分析に基づいた作業療法介入であることをしっかりと理解できるはずです。
高次脳機能障害における生活障害へ介入する作業療法士ならではの臨床推論についてまとめあげた、本邦初の書籍です。
関連情報
作業療法ジャーナル2021年55巻7号~10号
連載「生活障害の科学的分析から生まれるオーダーメイドな作業療法」
目次
監修の序・・・三村 將
編集の序・・・酒井 浩
略語一覧
執筆者一覧
第1章 作業療法における臨床推論・・・宮口英樹
1 作業療法と臨床推論
2 臨床推論の種類
3 作業療法に推論過程をどのように活かすか
4 作業療法推論における「統合と解釈」と高次脳機能障害
5 臨床推論の能力を高めるために
トピック VBPとSDM・・・宮口英樹
1 価値に基づく診療(VBP)
2 共同意思決定(SDM)
第2章 臨床推論の基礎と推論過程・・・酒井 浩
1 事象が何に起因するのかを特定する
2 事象を掘り下げる
3 作業療法における臨床推論の流れ
4 事象から予備的診断(仮説生成)までの流れ
5 予備的診断の検証(確認検査)
トピック 注意障害・記憶障害がある対象者へのアプローチ・・・中井秀昭
1 注意障害・記憶障害とリハビリテーション
2 注意障害に対するリハビリテーションのアプローチやエビデンス
3 記憶障害に対するリハビリテーションのアプローチやエビデンス
コラム 脳卒中および身体障害領域の臨床評価:評価編・・・尾藤祥子
1 WMFT(Wolf Motor Function Test)
2 MAL(Motor Activity Log)
コラム 脳卒中および身体障害領域の臨床評価:介入編・・・田丸佳希
1 リハビリテーションと運動学習
2 脳卒中リハビリテーションの代表的なファシリテーションテクニック
3 エビデンスに基づくCI療法
第3章 高次脳機能障害のアセスメント・・・酒井 浩
総論:脳の役割分担と高次脳機能障害
1 前頭葉の働きと高次脳機能障害
2 頭頂−後頭葉の働きと高次脳機能障害
3 側頭葉の働きと高次脳機能障害
各論
1 注意障害
2 半側空間無視
3 視覚失認
4 バリント症候群
5 記憶障害
6 失行症
7 ゲルストマン症候群および身体部位失認
8 前頭葉障害
トピック 左半側空間無視と最近の知見・・・大松聡子
1 半側空間無視の病態
2 机上検査における限界点
3 注意ネットワークの障害としての2つの選択反応課題(能動注意課題と受動注意課題)
4 視線計測から代償戦略の程度を評価する
5 左右反転画像提示における自由視認中の視線計測
トピック 視覚認知の障害とその評価―視覚失認・バリント症候群―・・・安永佐知歌
1 視覚認知に関わる脳
2 視覚失認の分類と評価
3 バリント症候群とその評価
4 その他の視覚認知障害
コラム 失語症の臨床評価と結果の解釈・・・酒井希代江
1 失語症の評価
2 評価の前に
3 病期における評価
4 標準失語症検査(SLTA)
5 実用コミュニケーション能力検査(CADL)
6 失語症とその他の原因による言語障害との鑑別
7 失語症者への対応
第4章 神経症状から考える臨床推論・・・髙橋守正
1 時期から考える
2 症状から考える
3 脳の血管支配
4 認知症と高次脳機能障害
トピック 失行症とその他の行為・行動の障害・・・塚越千尋
1 失行症
2 行為・行動の障害
3 介入方法の変遷
コラム 統合失調症とうつ病・・・真下いずみ
1 統合失調症
2 うつ病
第5章 レジュメにおける臨床推論の組み立て
レジュメ見本:右半球病変・・・酒井 浩
1 レジュメ作成の要旨
2 統合と解釈に至るまでのポイント
レジュメ見本:左半球病変・・・酒井 浩
1 レジュメ作成の要旨
2 統合と解釈に至るまでのポイント
レジュメの作成:基礎編・・・酒井 浩
1 レジュメ
2 レジュメ作成上の重要ポイント
3 「統合と解釈」を考えるための論理展開①
4 「統合と解釈」を考えるための論理展開②
レジュメの作成:応用編①・・・酒井 浩
1 レジュメ
2 情報の確認
レジュメの作成:応用編②・・・酒井 浩,横井賀津志
1 作業とは
2 人・環境・作業
3 評価と介入
4 レジュメ
トピック 社会的行動障害,意欲の障害,遂行機能障害をシステムの観点から捉える・・・山根伸吾
1 脳機能システム
2 病態メカニズムの考え方
コラム 意味のある作業,作業レベルの臨床評価・・・横井賀津志
1 作業ニーズ
2 作業ニーズを捉えるための評価ツール
3 作業遂行に関する評価ツール
第6章 臨床推論に役立つ画像の見方と考え方・・・大松聡子
1 脳内ネットワークと高次脳機能障害との関係
2 脳画像の読影に必要な白質線維
3 主要な高次脳機能障害
トピック 失読,失書,小児の読み書き障害・・・高畑脩平
1 概要
2 失読・失書の分類
3 読字の神経機構
4 書字の神経機構
コラム 妄想性人物誤認と周辺症候(奇妙な訴えをするもの)・・・中西英一
1 妄想性人物誤認とは
2 妄想性人物誤認の周辺症候
第7章 事例を通した推論過程の理解・・・酒井 浩
1 事例の見方
2 事例の概要
事例①:左後頭葉内側病変
1 カルテ情報
2 相談内容
3 推論過程
4 相談に対する回答
事例②:右頭頂葉病変
1 カルテ情報
2 相談内容
3 推論過程
4 相談に対する回答
事例③:右前頭葉病変
1 カルテ情報
2 相談内容
3 推論過程
4 相談に対する回答
5 統合と解釈を踏まえた介入方針の立案
索引
編集の序・・・酒井 浩
略語一覧
執筆者一覧
第1章 作業療法における臨床推論・・・宮口英樹
1 作業療法と臨床推論
2 臨床推論の種類
3 作業療法に推論過程をどのように活かすか
4 作業療法推論における「統合と解釈」と高次脳機能障害
5 臨床推論の能力を高めるために
トピック VBPとSDM・・・宮口英樹
1 価値に基づく診療(VBP)
2 共同意思決定(SDM)
第2章 臨床推論の基礎と推論過程・・・酒井 浩
1 事象が何に起因するのかを特定する
2 事象を掘り下げる
3 作業療法における臨床推論の流れ
4 事象から予備的診断(仮説生成)までの流れ
5 予備的診断の検証(確認検査)
トピック 注意障害・記憶障害がある対象者へのアプローチ・・・中井秀昭
1 注意障害・記憶障害とリハビリテーション
2 注意障害に対するリハビリテーションのアプローチやエビデンス
3 記憶障害に対するリハビリテーションのアプローチやエビデンス
コラム 脳卒中および身体障害領域の臨床評価:評価編・・・尾藤祥子
1 WMFT(Wolf Motor Function Test)
2 MAL(Motor Activity Log)
コラム 脳卒中および身体障害領域の臨床評価:介入編・・・田丸佳希
1 リハビリテーションと運動学習
2 脳卒中リハビリテーションの代表的なファシリテーションテクニック
3 エビデンスに基づくCI療法
第3章 高次脳機能障害のアセスメント・・・酒井 浩
総論:脳の役割分担と高次脳機能障害
1 前頭葉の働きと高次脳機能障害
2 頭頂−後頭葉の働きと高次脳機能障害
3 側頭葉の働きと高次脳機能障害
各論
1 注意障害
2 半側空間無視
3 視覚失認
4 バリント症候群
5 記憶障害
6 失行症
7 ゲルストマン症候群および身体部位失認
8 前頭葉障害
トピック 左半側空間無視と最近の知見・・・大松聡子
1 半側空間無視の病態
2 机上検査における限界点
3 注意ネットワークの障害としての2つの選択反応課題(能動注意課題と受動注意課題)
4 視線計測から代償戦略の程度を評価する
5 左右反転画像提示における自由視認中の視線計測
トピック 視覚認知の障害とその評価―視覚失認・バリント症候群―・・・安永佐知歌
1 視覚認知に関わる脳
2 視覚失認の分類と評価
3 バリント症候群とその評価
4 その他の視覚認知障害
コラム 失語症の臨床評価と結果の解釈・・・酒井希代江
1 失語症の評価
2 評価の前に
3 病期における評価
4 標準失語症検査(SLTA)
5 実用コミュニケーション能力検査(CADL)
6 失語症とその他の原因による言語障害との鑑別
7 失語症者への対応
第4章 神経症状から考える臨床推論・・・髙橋守正
1 時期から考える
2 症状から考える
3 脳の血管支配
4 認知症と高次脳機能障害
トピック 失行症とその他の行為・行動の障害・・・塚越千尋
1 失行症
2 行為・行動の障害
3 介入方法の変遷
コラム 統合失調症とうつ病・・・真下いずみ
1 統合失調症
2 うつ病
第5章 レジュメにおける臨床推論の組み立て
レジュメ見本:右半球病変・・・酒井 浩
1 レジュメ作成の要旨
2 統合と解釈に至るまでのポイント
レジュメ見本:左半球病変・・・酒井 浩
1 レジュメ作成の要旨
2 統合と解釈に至るまでのポイント
レジュメの作成:基礎編・・・酒井 浩
1 レジュメ
2 レジュメ作成上の重要ポイント
3 「統合と解釈」を考えるための論理展開①
4 「統合と解釈」を考えるための論理展開②
レジュメの作成:応用編①・・・酒井 浩
1 レジュメ
2 情報の確認
レジュメの作成:応用編②・・・酒井 浩,横井賀津志
1 作業とは
2 人・環境・作業
3 評価と介入
4 レジュメ
トピック 社会的行動障害,意欲の障害,遂行機能障害をシステムの観点から捉える・・・山根伸吾
1 脳機能システム
2 病態メカニズムの考え方
コラム 意味のある作業,作業レベルの臨床評価・・・横井賀津志
1 作業ニーズ
2 作業ニーズを捉えるための評価ツール
3 作業遂行に関する評価ツール
第6章 臨床推論に役立つ画像の見方と考え方・・・大松聡子
1 脳内ネットワークと高次脳機能障害との関係
2 脳画像の読影に必要な白質線維
3 主要な高次脳機能障害
トピック 失読,失書,小児の読み書き障害・・・高畑脩平
1 概要
2 失読・失書の分類
3 読字の神経機構
4 書字の神経機構
コラム 妄想性人物誤認と周辺症候(奇妙な訴えをするもの)・・・中西英一
1 妄想性人物誤認とは
2 妄想性人物誤認の周辺症候
第7章 事例を通した推論過程の理解・・・酒井 浩
1 事例の見方
2 事例の概要
事例①:左後頭葉内側病変
1 カルテ情報
2 相談内容
3 推論過程
4 相談に対する回答
事例②:右頭頂葉病変
1 カルテ情報
2 相談内容
3 推論過程
4 相談に対する回答
事例③:右前頭葉病変
1 カルテ情報
2 相談内容
3 推論過程
4 相談に対する回答
5 統合と解釈を踏まえた介入方針の立案
索引
書評
行動を理解し、脳機能と作業を結びつける
評者:中村春基(日本作業療法士協会、会長)
まずもって、上記タイトルの書籍が上梓されたことをうれしく思う。本書の特徴については、監修の三村 將氏が述べているが、酒井 浩氏のこれまでの臨床での経験、学び、そして臨床を思う気持ちが凝縮されている。新人は、臨床推論の重要性、そのまとめであるレジュメの紹介、振り返り、症状と損傷領域の対応表、トピックス、深堀りの作業等々、今後、何を、どのように学び、その結果がどうつながっていくのかを、本書を読むことでイメージできる。著者の多くが、この道のスペシャリストであり、読者がここに記述された内容の深みを納得できるまでは、努力してもある程度の臨床経験を要すると思うが、本書は自らの成長を確認するマイルストーンの一つであり、手元において自分の臨床推論と比較し、本書にない事象を発見されることを願っている。
私事として本書を振り返ると、推論過程はどうやら、昔から行っていたことと同じである。ほっとした次第である。しかし、本書の主題である高次脳機能障害の臨床推論になると、「歯が立たない」。リープマンの古典的分類、責任病巣といった知識では、複雑な脳機能障害を理解し切れないことが、本書を読むとよくわかる。私同様に、本書を読み、「焦り」を感じた読者が、本書をはじめ、最新の脳科学、高次脳機能障害に関する書籍に目を通す、あるいは、関連学会、研修会等に参画するようになれば、著者一同も本望であろう。
本書の索引を見ていただくとその特徴がよくわかる。たとえば、「観念失行」をみると、p53、p67、p109、p151、p224、p227とある。実は、この反複こそが、浅学の私の知識を繰り返し補完し、1~7章までを完読すると、先の「焦り」に対する、具体的な自己変容の方向性を示してくれる。各種の脳内ネットワークの記述は、詳細な解剖の知識の必要を自覚させ、そこから導かれる臨床推論は新鮮である。そして何よりも、それを作業療法の実践まで「つなげた」ことが本書の真髄といえる。
丁寧に記載された症例のレジュメ、観察の視点や検査結果の解釈、脳画像、ネットワーク理論に基づく推論は、あたかも、推理小説の物語性を感じる。聞きなれない単語に始めはまったくついていけない感じの読者もいると思うが、ここは「我慢」。読み進めていただければ、経験のどこかに触れることは間違いなくある。もちろん、担当している患者の障害と重ね合わせてお読みいただければ、さらに理解は進むだろう。
各章の紹介もしたいが、ぜひ、手元に置いて、読者それぞれの書評(感想)を著者にお届けいただければと思う。タイトルと齟齬のない内容であることは保証する。最後に、本書は高次脳機能障害の作業療法に焦点を当てているが、人の行動の理解、脳機能と作業を結びつける書籍として価値ある書籍である。ぜひ、多くの関係者に読まれ、活用されることを願っている。
「作業療法ジャーナル」vol.57 no.1(2023年1月号) (三輪書店)より転載
評者:中村春基(日本作業療法士協会、会長)
まずもって、上記タイトルの書籍が上梓されたことをうれしく思う。本書の特徴については、監修の三村 將氏が述べているが、酒井 浩氏のこれまでの臨床での経験、学び、そして臨床を思う気持ちが凝縮されている。新人は、臨床推論の重要性、そのまとめであるレジュメの紹介、振り返り、症状と損傷領域の対応表、トピックス、深堀りの作業等々、今後、何を、どのように学び、その結果がどうつながっていくのかを、本書を読むことでイメージできる。著者の多くが、この道のスペシャリストであり、読者がここに記述された内容の深みを納得できるまでは、努力してもある程度の臨床経験を要すると思うが、本書は自らの成長を確認するマイルストーンの一つであり、手元において自分の臨床推論と比較し、本書にない事象を発見されることを願っている。
私事として本書を振り返ると、推論過程はどうやら、昔から行っていたことと同じである。ほっとした次第である。しかし、本書の主題である高次脳機能障害の臨床推論になると、「歯が立たない」。リープマンの古典的分類、責任病巣といった知識では、複雑な脳機能障害を理解し切れないことが、本書を読むとよくわかる。私同様に、本書を読み、「焦り」を感じた読者が、本書をはじめ、最新の脳科学、高次脳機能障害に関する書籍に目を通す、あるいは、関連学会、研修会等に参画するようになれば、著者一同も本望であろう。
本書の索引を見ていただくとその特徴がよくわかる。たとえば、「観念失行」をみると、p53、p67、p109、p151、p224、p227とある。実は、この反複こそが、浅学の私の知識を繰り返し補完し、1~7章までを完読すると、先の「焦り」に対する、具体的な自己変容の方向性を示してくれる。各種の脳内ネットワークの記述は、詳細な解剖の知識の必要を自覚させ、そこから導かれる臨床推論は新鮮である。そして何よりも、それを作業療法の実践まで「つなげた」ことが本書の真髄といえる。
丁寧に記載された症例のレジュメ、観察の視点や検査結果の解釈、脳画像、ネットワーク理論に基づく推論は、あたかも、推理小説の物語性を感じる。聞きなれない単語に始めはまったくついていけない感じの読者もいると思うが、ここは「我慢」。読み進めていただければ、経験のどこかに触れることは間違いなくある。もちろん、担当している患者の障害と重ね合わせてお読みいただければ、さらに理解は進むだろう。
各章の紹介もしたいが、ぜひ、手元に置いて、読者それぞれの書評(感想)を著者にお届けいただければと思う。タイトルと齟齬のない内容であることは保証する。最後に、本書は高次脳機能障害の作業療法に焦点を当てているが、人の行動の理解、脳機能と作業を結びつける書籍として価値ある書籍である。ぜひ、多くの関係者に読まれ、活用されることを願っている。
「作業療法ジャーナル」vol.57 no.1(2023年1月号) (三輪書店)より転載
書評
高次脳機能障害を丁寧に紐解き、掘り下げていく
評者:種村留美(神戸大学大学院保健学研究科)
本書は、臨床で出合う高次脳機能障害の生活障害に対する推論思考過程について述べられたテキストである。項目立ては、第1章・第2章で作業療法の臨床推論の基礎と推論過程を、第3章で高次脳機能障害のアセスメント、第4章で神経症状から考える臨床推論、第5章ではレジュメにおける臨床推論の組み立て、第6章で臨床推論に役立つ画像の見方と考え方、最終章の第7章では事例を通した推論過程の理解という構成になっている。
臨床のなかでは、特に高次脳機能障害の症状は、「Why?(なぜ?)」「What?(これは何?)」「How?(どうして?)」というさまざまな臨床疑問が渦巻く。それを丁寧に紐解き、掘り下げていくのが臨床推論である。この臨床推論がうまくいくとクライエント一人ひとりにオーダーメイドの介入ができる。
作業療法は、障害を負った「ひと」のさまざまな歴史や環境、個人因子を把握したうえで行われていく。常日頃、教員の私は、授業のなかで幾度となく、「面接、観察、検査などの評価結果から患者さん全体を解釈し、治療に当たるんだよ」と念仏のようによく唱えているし、学生にとっては授業の実習レベルではなかなか統合と解釈までのイメージが湧かないのか、レポートの添削にはずいぶんと苦慮する。したがって、この「臨床推論」のテキストはたいへんありがたい。なぜなら、普段の私たちの評価結果の解釈や臨床結果を、臨床推論という学問のなかに落とし込み、エビデンスを明確にすることができるし、臨床推論の統合と解釈も述べてくれており、今までにはないテキストだからである。
高次脳機能障害の臨床推論過程は、帰納的方法と演繹的方法の組み合わせで行うことが述べられ、作業療法の臨床推論は、治療介入の効果を科学的推論に基づき、一人ひとりの作業的課題に焦点を当てた生活文脈のなかでこそ最も認められると説明している(p.9)。まさしくそうである。「統合と解釈」を行うためには、困りごとやうまくいかないなどの事象を「掘り下げる」ことが必要である。
時期から、症状から、評価結果から、等々、臨床推論を推し進めていく方法が記述されてあるから、学生にとっても理解が進むものと思われる。特に、第5章では、丁寧にレジュメの書き方が記されており、また、レジュメから臨床推論を考える方法などは、レジュメの書き方のバイブルといっても過言ではない。
さらに、第6章では、最近のトピックである高次脳機能障害の脳内ネットワークが記載されており、なかでも、高次脳機能障害の症状と損傷領域の対応表は従来のものよりも記載が詳細である。
そして、第7章では、高次脳機能障害の臨床症状が複雑な3つの事例について、セラピストから寄せられた臨床疑問を解き明かす臨床推論の過程が詳細に述べられており、その解き明かす過程が読んでいてとてもおもしろい。詳細はぜひ本書で読んでほしい。
「総合リハビリテーション」vol.51 no.2(2023年2月号)(医学書院)より転載
評者:種村留美(神戸大学大学院保健学研究科)
本書は、臨床で出合う高次脳機能障害の生活障害に対する推論思考過程について述べられたテキストである。項目立ては、第1章・第2章で作業療法の臨床推論の基礎と推論過程を、第3章で高次脳機能障害のアセスメント、第4章で神経症状から考える臨床推論、第5章ではレジュメにおける臨床推論の組み立て、第6章で臨床推論に役立つ画像の見方と考え方、最終章の第7章では事例を通した推論過程の理解という構成になっている。
臨床のなかでは、特に高次脳機能障害の症状は、「Why?(なぜ?)」「What?(これは何?)」「How?(どうして?)」というさまざまな臨床疑問が渦巻く。それを丁寧に紐解き、掘り下げていくのが臨床推論である。この臨床推論がうまくいくとクライエント一人ひとりにオーダーメイドの介入ができる。
作業療法は、障害を負った「ひと」のさまざまな歴史や環境、個人因子を把握したうえで行われていく。常日頃、教員の私は、授業のなかで幾度となく、「面接、観察、検査などの評価結果から患者さん全体を解釈し、治療に当たるんだよ」と念仏のようによく唱えているし、学生にとっては授業の実習レベルではなかなか統合と解釈までのイメージが湧かないのか、レポートの添削にはずいぶんと苦慮する。したがって、この「臨床推論」のテキストはたいへんありがたい。なぜなら、普段の私たちの評価結果の解釈や臨床結果を、臨床推論という学問のなかに落とし込み、エビデンスを明確にすることができるし、臨床推論の統合と解釈も述べてくれており、今までにはないテキストだからである。
高次脳機能障害の臨床推論過程は、帰納的方法と演繹的方法の組み合わせで行うことが述べられ、作業療法の臨床推論は、治療介入の効果を科学的推論に基づき、一人ひとりの作業的課題に焦点を当てた生活文脈のなかでこそ最も認められると説明している(p.9)。まさしくそうである。「統合と解釈」を行うためには、困りごとやうまくいかないなどの事象を「掘り下げる」ことが必要である。
時期から、症状から、評価結果から、等々、臨床推論を推し進めていく方法が記述されてあるから、学生にとっても理解が進むものと思われる。特に、第5章では、丁寧にレジュメの書き方が記されており、また、レジュメから臨床推論を考える方法などは、レジュメの書き方のバイブルといっても過言ではない。
さらに、第6章では、最近のトピックである高次脳機能障害の脳内ネットワークが記載されており、なかでも、高次脳機能障害の症状と損傷領域の対応表は従来のものよりも記載が詳細である。
そして、第7章では、高次脳機能障害の臨床症状が複雑な3つの事例について、セラピストから寄せられた臨床疑問を解き明かす臨床推論の過程が詳細に述べられており、その解き明かす過程が読んでいてとてもおもしろい。詳細はぜひ本書で読んでほしい。
「総合リハビリテーション」vol.51 no.2(2023年2月号)(医学書院)より転載


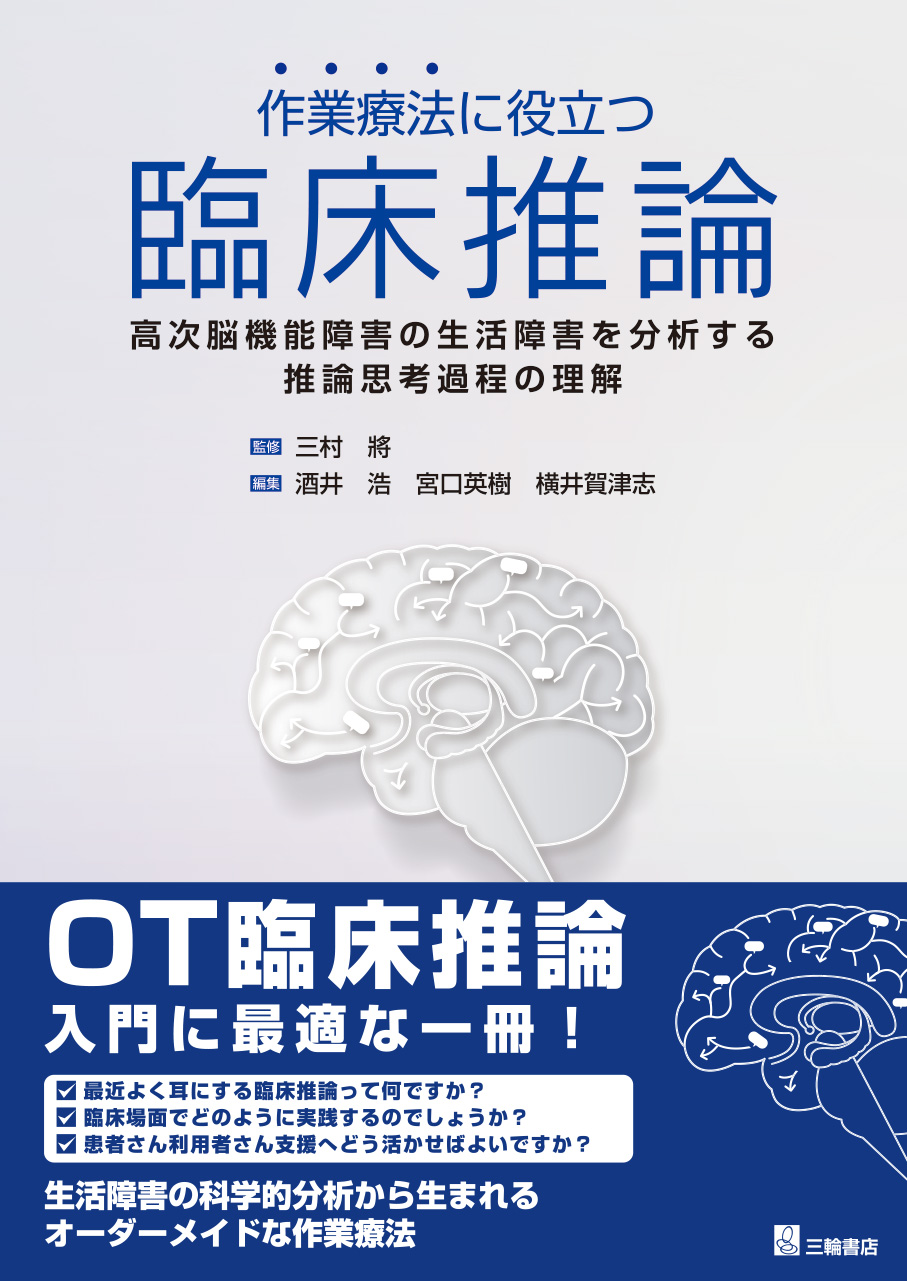



【監修】三村 將
【編集】酒井 浩、宮口英樹、横井賀津志