意思決定支援 こんなときどうする!?
内容紹介
誰も教えてくれなかった、患者とのコミュニケーションエラー問題。
その傾向と対策を、超具体的なケースを元に徹底解説
コミュニケーションを失敗するケースには一定のパターンがあり、それは裏を返せば犯しやすい過ちを知っておくことで失敗を未然に防げるケースが多いということです。
本書は著者が実際にかかわった意思決定支援における25のケーススタディで構成されています。会話の中での「もやもやポイント」「すれ違いポイント」「失敗ポイント」から、コミュニケーションがうまくいかない悩みの解決の糸口を提示します。
想像力が足りずに無意識のうちに相手を傷つけていたケース、医学的妥当性を振りかざして返り討ちに会ったケースなど、うまくいったケースも、うまくいかなかったケースも正直に再現しました。言葉遣いにも着目していただき、「いるよね、こういう医者」とか、たくさんの突っ込みを入れながら読んでください。
意思決定支援における数々の失敗例、成功例と真摯に向き合い、想像力を磨くことで、患者、家族の真のニーズがみえてきます。
目次
はじめに
I 失敗から学ぶコミュニケーション
1 本人が病状を否認しているケース
2 本人は病気を受容しているが、家族が諦めきれないケース
3 家族内の方針がバラバラで、話し合いが成立しないケース
4 自宅での看取りを望む余命の短い本人を、入院させようとする家族
5 自宅に帰りたい本人と、自宅は無理だと言う家族
6 最期まで一緒に過ごしたい家族と、一人でいたい本人
7 在宅支援者と病院担当者で意見が分かれたケース
8 何を望んでいるかを話してくれないがん末期のケース
9 何度も説明と同意を行ったにもかかわらず、死後に病状説明を求められたケース
10 家族の希望が高過ぎて医療者の説明を受け入れられないケース
11 家族が自分らの望む治療以外を受け入れないケース
12 前主治医の治療方針に固執し、主治医の説明を聞き入れないケース
13 主治医と担当看護師で意見が分かれたケース
II 相手の考えを想像したコミュニケーション
A 疾患別のアプローチ
1 がん終末期のケース
2 誤嚥性肺炎を繰り返しているケース
3 神経難病の診断を受けて間もないケース
4 嚥下が難しいにもかかわらず、 家族が経口摂取を諦められないケース
5 繰り返し心不全で入院しているケース
6 療養方針が分岐点に立った老衰のケース
B 状況別のアプローチ
1 病棟主治医を引き継いだ場合
2 在宅医療の初回介入時
3 在宅医療で病院搬送を迷う場合
C 想像を広げて一歩踏み込んだアプローチ
1 話し合いを通じて得られた気づきが方針転換につながったケース
2 状況から想像する
3 意図的に投げかける
III 相手の考えていることを想像するヒントの探し方
1 相手に「興味をもつ」ことと「観察する」こと
2 相手の本音はどこにある?
3 「未来」を考えるうえで「過去」を振り返る
おわりに
I 失敗から学ぶコミュニケーション
1 本人が病状を否認しているケース
2 本人は病気を受容しているが、家族が諦めきれないケース
3 家族内の方針がバラバラで、話し合いが成立しないケース
4 自宅での看取りを望む余命の短い本人を、入院させようとする家族
5 自宅に帰りたい本人と、自宅は無理だと言う家族
6 最期まで一緒に過ごしたい家族と、一人でいたい本人
7 在宅支援者と病院担当者で意見が分かれたケース
8 何を望んでいるかを話してくれないがん末期のケース
9 何度も説明と同意を行ったにもかかわらず、死後に病状説明を求められたケース
10 家族の希望が高過ぎて医療者の説明を受け入れられないケース
11 家族が自分らの望む治療以外を受け入れないケース
12 前主治医の治療方針に固執し、主治医の説明を聞き入れないケース
13 主治医と担当看護師で意見が分かれたケース
II 相手の考えを想像したコミュニケーション
A 疾患別のアプローチ
1 がん終末期のケース
2 誤嚥性肺炎を繰り返しているケース
3 神経難病の診断を受けて間もないケース
4 嚥下が難しいにもかかわらず、 家族が経口摂取を諦められないケース
5 繰り返し心不全で入院しているケース
6 療養方針が分岐点に立った老衰のケース
B 状況別のアプローチ
1 病棟主治医を引き継いだ場合
2 在宅医療の初回介入時
3 在宅医療で病院搬送を迷う場合
C 想像を広げて一歩踏み込んだアプローチ
1 話し合いを通じて得られた気づきが方針転換につながったケース
2 状況から想像する
3 意図的に投げかける
III 相手の考えていることを想像するヒントの探し方
1 相手に「興味をもつ」ことと「観察する」こと
2 相手の本音はどこにある?
3 「未来」を考えるうえで「過去」を振り返る
おわりに
書評
「意思決定支援 こんなときどうする!?」を読む――どうすれば納得できるのか
評者:浜本康夫 (東京科学大学大学院臨床腫瘍学分野)
ある日の昼下がり,私はランチをどうするか迷っていた。コンビニ弁当やカップ麺で急いで済ませるか,職員に好評のキッチンカーのカレーか。同僚の何気ないおススメもあり寒風の中,行列のできているキッチンカーに並ぶことにした。そう,どんな些細な「意思決定」にもさまざまなプロセスと結果がある。医療現場では,患者や家族が向き合う意思決定に支援が日々繰り返されている。
そんななか,以前一緒に働いていた水野慎大氏から著書の『意思決定支援 こんなときどうする!?』をいただいた。本書では意思決定支援の本質とそのプロセスが,医療現場の豊富なケースを通じて解説されている。水野氏のキャリアは多彩で,地域医療,大学病院で教育・研究,専門医として活躍後に訪問診療を経て,現在は「おうちにかえろう。病院」の院長である。ご存じの人も多いかもしれないが,この病院は,東京板橋で既存の施設とは一線を画すユニークな医療を実践しておりメディアでも話題になっている。わたしも病院見学に行き,その斬新なアイデアとリベラルな姿勢に驚いた。本書には,これらの豊富な経験が随所に生き生きと描かれている。
第Ⅰ章と第Ⅱ章の「失敗から学ぶコミュニケーション」,「相手の考えを想像したコミュニケーション」では著者が出会った多くのケースを誌面で再現し,医療者が日々直面する難しい選択をどう支援するかを具体的に示している。失敗談に基づく解説は,医療者にとって共感できる内容である。つい「医学的正しさ」という武器を振り回しがちな自分の日常診療を振り返り反省させられる。
第Ⅲ章「相手の考えていることを想像するヒントの探し方」が,本書の集大成である。意思決定支援において「相手に興味をもつこと」「観察する」ことが重要である一方で,私たち医療者は「尋問モード」になっていることに注意喚起し,「医療者にとっての正解に到達しようとしている」ことへの警鐘を鳴らす。「雑談モード」を通じて相手に寄り添い,「医療者は患者のことを何も知らない」という当たり前のことを前提に「相手の行動に着目」し,「何を言っているのか,よりも,何をしているか」に注目する。病院と在宅医療双方の現場を知って経験してきた著者の強みで一読の価値がある。
本書には,現場での経験に裏打ちされた「技」を,単なるエピソードに終わらせるのではなく,理論化し体系化しようとする姿勢がある。これは著者が医療現場だけではなく,大学で教育者であり研究者として悪戦苦闘した経験が大きく関係していると思う。本書は,緩和ケアに携わる医療者のみならず,あらゆる医療現場で働く人々にとって,日々の課題に向き合うための強力な指南書となるであろう。
さて,悩んでゲットした特製カレーはスパイスが効いて身体も心も温まり自分の意思決定に納得できた。午後の診療は,大きな意思決定を要する面談だったが,優しい気持ちで相手の本音を聞き出すことができた。心のなかで本書と同僚に感謝した。
「緩和ケア」Vol.35 No.2 (2025年3月号)(青海社)より転載
評者:浜本康夫 (東京科学大学大学院臨床腫瘍学分野)
ある日の昼下がり,私はランチをどうするか迷っていた。コンビニ弁当やカップ麺で急いで済ませるか,職員に好評のキッチンカーのカレーか。同僚の何気ないおススメもあり寒風の中,行列のできているキッチンカーに並ぶことにした。そう,どんな些細な「意思決定」にもさまざまなプロセスと結果がある。医療現場では,患者や家族が向き合う意思決定に支援が日々繰り返されている。
そんななか,以前一緒に働いていた水野慎大氏から著書の『意思決定支援 こんなときどうする!?』をいただいた。本書では意思決定支援の本質とそのプロセスが,医療現場の豊富なケースを通じて解説されている。水野氏のキャリアは多彩で,地域医療,大学病院で教育・研究,専門医として活躍後に訪問診療を経て,現在は「おうちにかえろう。病院」の院長である。ご存じの人も多いかもしれないが,この病院は,東京板橋で既存の施設とは一線を画すユニークな医療を実践しておりメディアでも話題になっている。わたしも病院見学に行き,その斬新なアイデアとリベラルな姿勢に驚いた。本書には,これらの豊富な経験が随所に生き生きと描かれている。
第Ⅰ章と第Ⅱ章の「失敗から学ぶコミュニケーション」,「相手の考えを想像したコミュニケーション」では著者が出会った多くのケースを誌面で再現し,医療者が日々直面する難しい選択をどう支援するかを具体的に示している。失敗談に基づく解説は,医療者にとって共感できる内容である。つい「医学的正しさ」という武器を振り回しがちな自分の日常診療を振り返り反省させられる。
第Ⅲ章「相手の考えていることを想像するヒントの探し方」が,本書の集大成である。意思決定支援において「相手に興味をもつこと」「観察する」ことが重要である一方で,私たち医療者は「尋問モード」になっていることに注意喚起し,「医療者にとっての正解に到達しようとしている」ことへの警鐘を鳴らす。「雑談モード」を通じて相手に寄り添い,「医療者は患者のことを何も知らない」という当たり前のことを前提に「相手の行動に着目」し,「何を言っているのか,よりも,何をしているか」に注目する。病院と在宅医療双方の現場を知って経験してきた著者の強みで一読の価値がある。
本書には,現場での経験に裏打ちされた「技」を,単なるエピソードに終わらせるのではなく,理論化し体系化しようとする姿勢がある。これは著者が医療現場だけではなく,大学で教育者であり研究者として悪戦苦闘した経験が大きく関係していると思う。本書は,緩和ケアに携わる医療者のみならず,あらゆる医療現場で働く人々にとって,日々の課題に向き合うための強力な指南書となるであろう。
さて,悩んでゲットした特製カレーはスパイスが効いて身体も心も温まり自分の意思決定に納得できた。午後の診療は,大きな意思決定を要する面談だったが,優しい気持ちで相手の本音を聞き出すことができた。心のなかで本書と同僚に感謝した。
「緩和ケア」Vol.35 No.2 (2025年3月号)(青海社)より転載
書評
患者に寄り添う看護の道標 ー 意思決定支援と伴走するケア
評者:宇都宮宏子 (在宅ケア移行支援研究所)
目次を開いて, 「あるある」と感じたケースから,読み進めてみました。内容はわかりやすく,心にスーッと沁みてきます。自分の思考のクセが浮き彫りになるかもしれません。
医療者は,病態予測ができて,未来が見通せる分,焦りがちです。 「あれ?」とモヤモヤした時に,ちょっと立ち止まり,療養者さんの心模様を想像してみることを,多職種に発信してきました。この本は,まさに具体的な実践への道案内になりそうです。
私は,訪問看護師として,生きづらさを抱えながらも「最期までここがええ」 と願う人々のために,家族や在宅支援者と話し合いを繰り返し,その人生の旅路に伴走する看護に取り組んできました。しかし,療養者が入院すると,帰ってこない「片道切符の入院」が多い状況にも直面してきました。入院医療から暮らしの場へ移行するためには,何らかの支援,マネジメントが必要ではないかと考え,2002年,大学病院で「おうちへ帰ろう」という活動を始め,全国へ普及するため2012年に独立起業しています。
病院で見えた風景は,人生の大事な分岐点であるにもかかわらず,本人抜きで,家族とだけ相談して決めているケースが多いものでした。退院支援が必要な患者には,医師からの説明がいわゆる「バッドニュース」になる
ことが少なくありません。
皆さんの現場では,外来・入院の場面で医師から病状説明を受け,これからの治療や療養の方向性を考えていく時,患者,家族に寄り添った意思決定支援ができていますか? 病院は,本人にとっては非日常の空間であり,住まいのように,思いを語りやすい場とはいえません。しかし,病気や,状態の変化を知り,これからどんな軌跡をへて,人生の幕引きとなるのかを予測することができるには,病院の外来や,入院の場面がその節目となります。
看護師として,患者のそばを離れず,寄り添い,「どう生きるか」を共に考え,生活を再構築する支援が地域包括ケア時代における大切な看護の役割だと確信して活動しています。
本書は,現場で迷った時や,研修でのテキストとしても活用できる構成になっています。
Ⅰ . 失敗から学ぶコミュニケーションでは,事例紹介後,支援者と本人・家族とのやり取り,モヤモヤポイント,すれ違いポイントを示し,解説を通じて解決への糸口が書かれています。
Ⅱ . 相手の考えを想像したコミュニケーションでは,臨床現場でのやり取りと,陥りがちな患者・家族・医療者の思考回路や見えている風景がイラストで示され,患者本人の人生を伴走する支援者として,なるほどと頷きながら,深く学ぶポイントが満載です。
Ⅲ . 相手の考えていることを想像するヒントの探し方は,人生という旅路を歩む方と伴走していく過程で,何度か訪れる分岐点での意思決定支援,そしてACPへの支援が書かれています。
これまで(過去)を振り返る中で,未来につなげたい価値や希望だけでなく家族としての物語も浮かび上がります。つらい場面でも,本人・家族が折り合いをつけながら,暮らし,生ききることに,チームとして伴走する皆さんのバイブルとなる一冊です。
「オン・ナーシング」Vol.3 No.6 (December 2024)(看護の科学新社)より転載
評者:宇都宮宏子 (在宅ケア移行支援研究所)
目次を開いて, 「あるある」と感じたケースから,読み進めてみました。内容はわかりやすく,心にスーッと沁みてきます。自分の思考のクセが浮き彫りになるかもしれません。
医療者は,病態予測ができて,未来が見通せる分,焦りがちです。 「あれ?」とモヤモヤした時に,ちょっと立ち止まり,療養者さんの心模様を想像してみることを,多職種に発信してきました。この本は,まさに具体的な実践への道案内になりそうです。
私は,訪問看護師として,生きづらさを抱えながらも「最期までここがええ」 と願う人々のために,家族や在宅支援者と話し合いを繰り返し,その人生の旅路に伴走する看護に取り組んできました。しかし,療養者が入院すると,帰ってこない「片道切符の入院」が多い状況にも直面してきました。入院医療から暮らしの場へ移行するためには,何らかの支援,マネジメントが必要ではないかと考え,2002年,大学病院で「おうちへ帰ろう」という活動を始め,全国へ普及するため2012年に独立起業しています。
病院で見えた風景は,人生の大事な分岐点であるにもかかわらず,本人抜きで,家族とだけ相談して決めているケースが多いものでした。退院支援が必要な患者には,医師からの説明がいわゆる「バッドニュース」になる
ことが少なくありません。
皆さんの現場では,外来・入院の場面で医師から病状説明を受け,これからの治療や療養の方向性を考えていく時,患者,家族に寄り添った意思決定支援ができていますか? 病院は,本人にとっては非日常の空間であり,住まいのように,思いを語りやすい場とはいえません。しかし,病気や,状態の変化を知り,これからどんな軌跡をへて,人生の幕引きとなるのかを予測することができるには,病院の外来や,入院の場面がその節目となります。
看護師として,患者のそばを離れず,寄り添い,「どう生きるか」を共に考え,生活を再構築する支援が地域包括ケア時代における大切な看護の役割だと確信して活動しています。
本書は,現場で迷った時や,研修でのテキストとしても活用できる構成になっています。
Ⅰ . 失敗から学ぶコミュニケーションでは,事例紹介後,支援者と本人・家族とのやり取り,モヤモヤポイント,すれ違いポイントを示し,解説を通じて解決への糸口が書かれています。
Ⅱ . 相手の考えを想像したコミュニケーションでは,臨床現場でのやり取りと,陥りがちな患者・家族・医療者の思考回路や見えている風景がイラストで示され,患者本人の人生を伴走する支援者として,なるほどと頷きながら,深く学ぶポイントが満載です。
Ⅲ . 相手の考えていることを想像するヒントの探し方は,人生という旅路を歩む方と伴走していく過程で,何度か訪れる分岐点での意思決定支援,そしてACPへの支援が書かれています。
これまで(過去)を振り返る中で,未来につなげたい価値や希望だけでなく家族としての物語も浮かび上がります。つらい場面でも,本人・家族が折り合いをつけながら,暮らし,生ききることに,チームとして伴走する皆さんのバイブルとなる一冊です。
「オン・ナーシング」Vol.3 No.6 (December 2024)(看護の科学新社)より転載


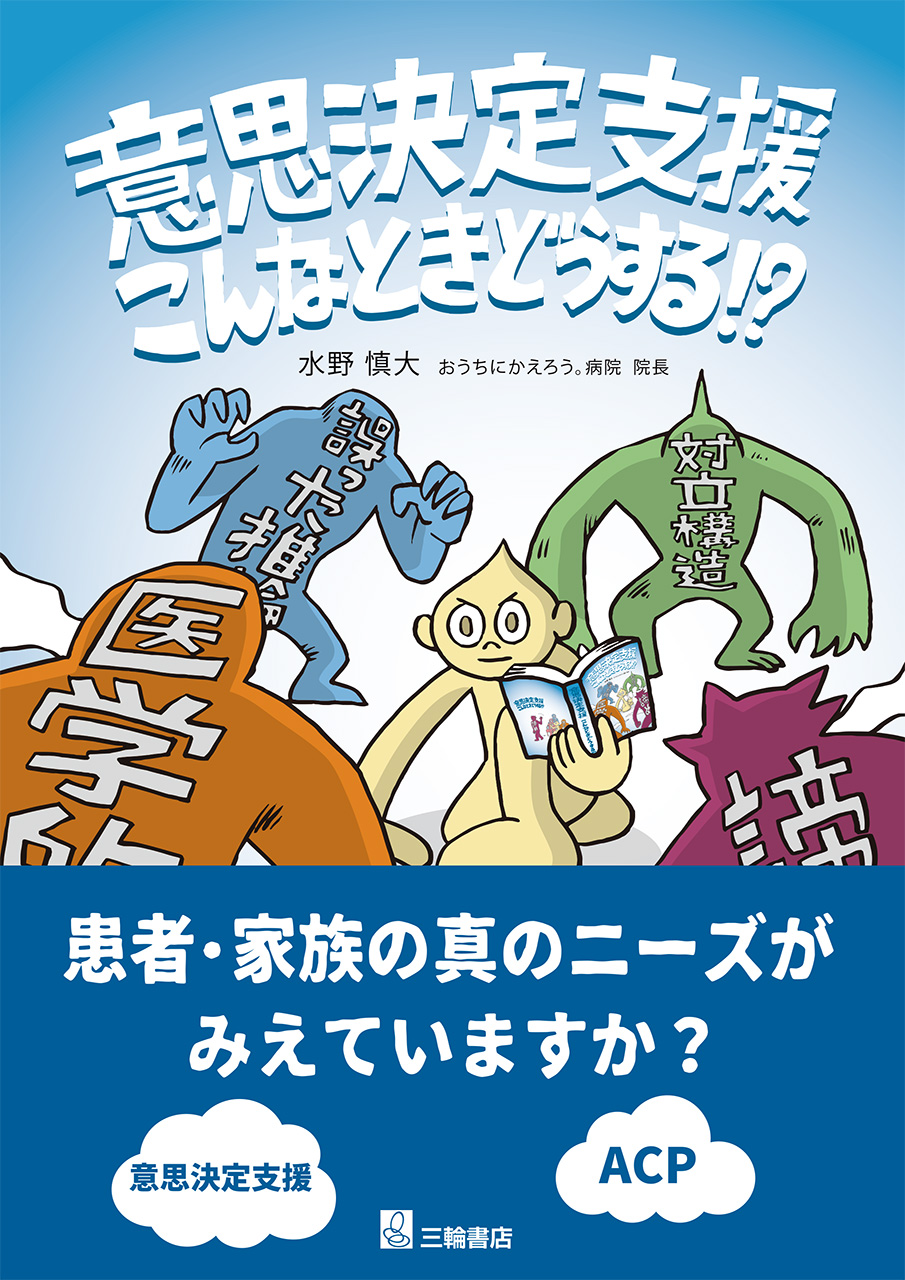


【著】水野慎大(おうちにかえろう。病院 院長)