認知症のある人の生活と作業療法【第3版】
定価:3,850円(本体3,500円+税)
商品コード: ISBN978-4-89590-829-0
内容紹介
認知症のある人が安定した日々を過ごせる支援を!好評書の第3版!
認知症と診断されても、毎日、24時間、これからずっと認知症… というわけではなく、認知症はその人の一部なのです。症状に振り回されない時は、以前と変わらないその人も存在します。認知症のある人は、毎日の生活で困難なことがあっても、そこだけ手が借りられれば、その先は生活できることが多いのです。作業療法士は認知症のある人の生活を観察して、その困難なポイントを見出します。これを「生活行為の工程分析」と呼びます。全面改訂した第3版となる本書では、この「工程分析」の方法を、事例と共に詳しく追記しています。また他にも、認知症に罹患しても、作業療法士や周囲の支援によって、これまでの人生経験を活かしながら本人らしく暮らす事例を多く紹介しています。
作業療法士養成課程の教科書として誕生した本書は、より実践的な内容へと改訂を重ねてきました。第3版では、臨床経験の豊富な谷川氏を共著者にむかえ、事例を増やし、より幅広い層に理解しやすい内容となりました。支援の考え方や支援方法は、作業療法士のみならず、関連職種にも参考になるものとなっています。作業療法の初学者はもちろんのこと、介護をする家族や、認知症支援に関わる多職種にも、ぜひ読んでもらいたい一冊です。
目次
第1章 認知症のある人に対する作業療法
1—1 認知症のある人に対する作業療法の目的
1—1—1 生活行為を遂行すること
1—1—2 その人らしく生きること
1—2 認知症のある人に対する作業療法事例
1—3 認知症のある人と支援者の関わり
1—3—1 認知症のある人と病院の治療環境
1—3—2 尊厳を大切に―パーソンセンタード・ケア
1—3—3 支援者はどのように関わるか
1—3—4 作業療法にあたって念頭に置くこと
第2章 認知症のある人はどのような人か
2—1 認知症のある人はどのような人か
2—1—1 高齢者で人生経験が豊かな人である
2—1—2 認知症という病がある人である
2—1—3 主体性を保ちにくい人である
2—2 どのような時に元気なのか?
2—2—1 24時間困り続けているわけではない
2—2—2 認知症のある「人」に出会う
第3章 高齢期にある人とは?
3—1 高齢期とは
3—2 平均寿命と健康寿命
3—3 高齢者自身がつくる豊かな生活
3—3—1 「衰退」と「成熟」
3—3—2 生活を楽しむ高齢者
3—3—3 持病と高齢者
3—4 老 化
3—4—1 老化と加齢に伴う変化
3—4—2 老化と疾病
3—5 老年期の心理(高齢期うつ病・うつ状態)
3—6 老化に起因する不自由
3—6—1 ADLにおける不自由
3—6—2 IADLにおける不自由
3—6—3 不自由を知恵で乗り越える
3—7 地域関連、社会参加
3—8 高齢者の暮らし
第4章 認知症を取り巻く社会の歴史と背景
4—1 認知症の歴史
4—1—1 恍惚の人
4—1—2 認知症専門病棟
4—1—3 身体拘束禁止
4—1—4 居場所の拡大
4—1—5 年表と関連資料
4—2 認知症基本法の成立
4—3 共生する社会を目指して
第5章 認知症の基礎知識
5—1 認知症とは
5—1—1 認知症の定義と診断基準
5—1—2 疫 学
5—1—3 原因疾患と分類
5—1—4 治療可能な認知症(treatable dementia)
5—1—5 4大認知症
5—2 認知症の症状
5—2—1 認知機能障害
5—2—2 行動・心理症状(BPSD)
5—3 認知症の治療
5—3—1 薬物療法
5—3—2 非薬物療法
第6章 主な認知症と作業療法
6—1 アルツハイマー病(Alzheimer’s Disease:AD)
6—1—1 疾患の概要
6—1—2 作業療法との関連
6—1—3 アルツハイマー病のある人の作業療法事例
6—2 血管性認知症(vascular dementia:VaD)
6—2—1 疾患の概要
6—2—2 作業療法との関連
6—2—3 血管性認知症のある人の作業療法事例
6—3 レビー小体型認知症(dementia with Lewy Bodies:DLB)
6—3—1 疾患の概要
6—3—2 作業療法との関連
6—3—3 レビー小体型認知症のある人の作業療法事例
6—4 前頭側頭型認知症(frontotemporal dementia:FTD)
6—4—1 疾患の概要
6—4—2 作業療法との関連
6—4—3 前頭側頭型認知症のある人の作業療法事例
6—5 軽度認知障害(mild cognitive impairment:MCI)
6—5—1 疾患の概要
6—5—2 作業療法との関連
第7章 評 価
7—1 生活する人を評価する
7—1—1 生活する人とは?
7—1—2 評価の出発点―Kさんの生活行為を聞き取る
7—2 情報の収集
7—3 面 接
7—3—1 なぜ面接が必要か
7—3—2 面接の方法
7—3—3 家族面接
7—4 観 察
7—4—1 なぜ観察が必要か
7—4—2 何をどう観察するか
7—4—3 観察記録
7—5 検査・測定
7—5—1 なぜ検査が必要か
7—5—2 認知機能の評価尺度
7—5—3 認知機能以外の評価尺度
7—5—4 軽度認知障害に関連する評価尺度
7—5—5 検査の実際―HDS-Rを例に
7—6 評価のまとめ
7—6—1 なぜICFでまとめるか
7—6—2 どのように考察するか
7—6—3 作業療法計画
7—6—4 再評価
7—6—5 最終評価
7—7 生活行為向上マネジメント
第8章 生活行為の工程分析と活用―作業療法技術を生かす
8—1 なぜ,生活行為の工程分析が必要か
8—2 生活行為と作業療法技術
8—3 生活行為の連続性
8—3—1 生活行為の固有性と連続性
8—3—2 生活行為と認知症の影響
8—4 生活行為に活かす作業療法技術
8—4—1 生活行為の焦点化の第一歩
8—4—2 焦点化された生活行為と工程分析
8—4—3 生活行為の工程分析の視点
8—5 工程分析
8—6 工程分析を用いた直接援助の技術的側面
8—6—1 Lさんの生活障害
8—6—2 本人の希望と現実
8—6—3 娘に行った提案
8—6—4 援助の解説
8—7 工程分析を用いた間接援助の技術的側面
8—8 工程分析の発展性
8—9 作業療法技術としての工程分析
第9章 介入と援助
9—1 作業療法士の関わりのポイント
9—1—1 環境を調整する
9—1—2 できることをして生活する
9—1—3 手続き記憶を生かす
9—1—4 周囲の環境との架け橋になる
9—1—5 認知症のある人に比較的保たれている機能
9—2 認知機能障害に対する援助
9—2—1 近時記憶障害に対する援助
9—2—2 見当識障害に対する援助
9—3 行動・心理症状(BPSD)に対する援助
9—3—1 外出(徘徊)への関わり
9—3—2 拒否への関わり
9—3—3 不潔行為への関わり
9—3—4 不安への関わり
9—3—5 妄想の捉え方
9—4 保たれている機能に対するアプローチ
9—4—1 感情と感情の記憶
9—4—2 基本的運動機能
9—4—3 社会性・社会的動作
9—4—4 手続き記憶
9—4—5 遠隔記憶
9—5 基本的生活に対する援助
9—5—1 安全な生活から普段の生活へ
9—5—2 基本動作に対する援助
9—5—3 座 位
9—5—4 歩 行
9—5—5 食 事
9—5—6 排 泄
9—5—7 入 浴
9—5—8 更 衣
9—5—9 整 容
9—6 IADLに対する援助
9—6—1 食事の準備、食事作り、後片づけ
9—6—2 洗 濯
9—6—3 買い物
9—6—4 掃 除
9—6—5 片づけ、整理
9—6—6 ごみ出し
9—7 その人にとって意味のある生活行為
9—8 役割活動の援助
9—9 対人関係を構築する援助
9—10 余暇活動に対する援助
9—10—1 レクリエーション
9—10—2 趣味活動
9—11 環境調整
9—11—1 普段の生活
9—11—2 建築環境の指針
9—11—3 看護覚え書
9—11—4 作業療法と環境調整
第10章 作業療法は参加に向かって
10—1 ICFと活動・参加
10—1—1 生活行為と参加の関係
10—1—2 つながりを見出す
10—2 コロナ禍を経験後の参加
10—3 人とのつながりから参加へ
10—4 地域の交流の場つくり
10—4—1 認知症にやさしい図書館
10—5 認知症のある人の有償ボランティア
10—6 楽しみがつくりだす仲間
第11章 家族に対する支援
11—1 家族支援と日本の動向
11—2 家族のおかれている状況
11—2—1 介護者の多様化と孤立化
11—2—2 高齢者のみ世帯の増加
11—2—3 家族が医療や福祉と出会うまでの期間
11—3 家族の心理
11—4 家族支援の目標
11—5 家族支援の具体的内容
11—5—1 作業療法士による家族を対象とした支援
11—5—2 家族の歴史を考慮
11—5—3 家族を作業療法士が支援する
11—6 家族をとりまく支援①―一体的支援プログラム
11—7 家族をとりまく支援②―さまざまな支援体制
11—7—1 認知症カフェ
11—7—2 認知症家族交流会(家族教室)
11—7—3 地域包括支援センター
11—7—4 認知症初期集中支援チーム
11—7—5 認知症地域支援推進員
11—7—6 認知症介護経験者による電話相談
11—7—7 認知症の人と家族の会
11—7—8 男性介護者と支援者との全国ネットワーク
11—7—9 レビー小体型認知症サポートネットワーク
1—1 認知症のある人に対する作業療法の目的
1—1—1 生活行為を遂行すること
1—1—2 その人らしく生きること
1—2 認知症のある人に対する作業療法事例
1—3 認知症のある人と支援者の関わり
1—3—1 認知症のある人と病院の治療環境
1—3—2 尊厳を大切に―パーソンセンタード・ケア
1—3—3 支援者はどのように関わるか
1—3—4 作業療法にあたって念頭に置くこと
第2章 認知症のある人はどのような人か
2—1 認知症のある人はどのような人か
2—1—1 高齢者で人生経験が豊かな人である
2—1—2 認知症という病がある人である
2—1—3 主体性を保ちにくい人である
2—2 どのような時に元気なのか?
2—2—1 24時間困り続けているわけではない
2—2—2 認知症のある「人」に出会う
第3章 高齢期にある人とは?
3—1 高齢期とは
3—2 平均寿命と健康寿命
3—3 高齢者自身がつくる豊かな生活
3—3—1 「衰退」と「成熟」
3—3—2 生活を楽しむ高齢者
3—3—3 持病と高齢者
3—4 老 化
3—4—1 老化と加齢に伴う変化
3—4—2 老化と疾病
3—5 老年期の心理(高齢期うつ病・うつ状態)
3—6 老化に起因する不自由
3—6—1 ADLにおける不自由
3—6—2 IADLにおける不自由
3—6—3 不自由を知恵で乗り越える
3—7 地域関連、社会参加
3—8 高齢者の暮らし
第4章 認知症を取り巻く社会の歴史と背景
4—1 認知症の歴史
4—1—1 恍惚の人
4—1—2 認知症専門病棟
4—1—3 身体拘束禁止
4—1—4 居場所の拡大
4—1—5 年表と関連資料
4—2 認知症基本法の成立
4—3 共生する社会を目指して
第5章 認知症の基礎知識
5—1 認知症とは
5—1—1 認知症の定義と診断基準
5—1—2 疫 学
5—1—3 原因疾患と分類
5—1—4 治療可能な認知症(treatable dementia)
5—1—5 4大認知症
5—2 認知症の症状
5—2—1 認知機能障害
5—2—2 行動・心理症状(BPSD)
5—3 認知症の治療
5—3—1 薬物療法
5—3—2 非薬物療法
第6章 主な認知症と作業療法
6—1 アルツハイマー病(Alzheimer’s Disease:AD)
6—1—1 疾患の概要
6—1—2 作業療法との関連
6—1—3 アルツハイマー病のある人の作業療法事例
6—2 血管性認知症(vascular dementia:VaD)
6—2—1 疾患の概要
6—2—2 作業療法との関連
6—2—3 血管性認知症のある人の作業療法事例
6—3 レビー小体型認知症(dementia with Lewy Bodies:DLB)
6—3—1 疾患の概要
6—3—2 作業療法との関連
6—3—3 レビー小体型認知症のある人の作業療法事例
6—4 前頭側頭型認知症(frontotemporal dementia:FTD)
6—4—1 疾患の概要
6—4—2 作業療法との関連
6—4—3 前頭側頭型認知症のある人の作業療法事例
6—5 軽度認知障害(mild cognitive impairment:MCI)
6—5—1 疾患の概要
6—5—2 作業療法との関連
第7章 評 価
7—1 生活する人を評価する
7—1—1 生活する人とは?
7—1—2 評価の出発点―Kさんの生活行為を聞き取る
7—2 情報の収集
7—3 面 接
7—3—1 なぜ面接が必要か
7—3—2 面接の方法
7—3—3 家族面接
7—4 観 察
7—4—1 なぜ観察が必要か
7—4—2 何をどう観察するか
7—4—3 観察記録
7—5 検査・測定
7—5—1 なぜ検査が必要か
7—5—2 認知機能の評価尺度
7—5—3 認知機能以外の評価尺度
7—5—4 軽度認知障害に関連する評価尺度
7—5—5 検査の実際―HDS-Rを例に
7—6 評価のまとめ
7—6—1 なぜICFでまとめるか
7—6—2 どのように考察するか
7—6—3 作業療法計画
7—6—4 再評価
7—6—5 最終評価
7—7 生活行為向上マネジメント
第8章 生活行為の工程分析と活用―作業療法技術を生かす
8—1 なぜ,生活行為の工程分析が必要か
8—2 生活行為と作業療法技術
8—3 生活行為の連続性
8—3—1 生活行為の固有性と連続性
8—3—2 生活行為と認知症の影響
8—4 生活行為に活かす作業療法技術
8—4—1 生活行為の焦点化の第一歩
8—4—2 焦点化された生活行為と工程分析
8—4—3 生活行為の工程分析の視点
8—5 工程分析
8—6 工程分析を用いた直接援助の技術的側面
8—6—1 Lさんの生活障害
8—6—2 本人の希望と現実
8—6—3 娘に行った提案
8—6—4 援助の解説
8—7 工程分析を用いた間接援助の技術的側面
8—8 工程分析の発展性
8—9 作業療法技術としての工程分析
第9章 介入と援助
9—1 作業療法士の関わりのポイント
9—1—1 環境を調整する
9—1—2 できることをして生活する
9—1—3 手続き記憶を生かす
9—1—4 周囲の環境との架け橋になる
9—1—5 認知症のある人に比較的保たれている機能
9—2 認知機能障害に対する援助
9—2—1 近時記憶障害に対する援助
9—2—2 見当識障害に対する援助
9—3 行動・心理症状(BPSD)に対する援助
9—3—1 外出(徘徊)への関わり
9—3—2 拒否への関わり
9—3—3 不潔行為への関わり
9—3—4 不安への関わり
9—3—5 妄想の捉え方
9—4 保たれている機能に対するアプローチ
9—4—1 感情と感情の記憶
9—4—2 基本的運動機能
9—4—3 社会性・社会的動作
9—4—4 手続き記憶
9—4—5 遠隔記憶
9—5 基本的生活に対する援助
9—5—1 安全な生活から普段の生活へ
9—5—2 基本動作に対する援助
9—5—3 座 位
9—5—4 歩 行
9—5—5 食 事
9—5—6 排 泄
9—5—7 入 浴
9—5—8 更 衣
9—5—9 整 容
9—6 IADLに対する援助
9—6—1 食事の準備、食事作り、後片づけ
9—6—2 洗 濯
9—6—3 買い物
9—6—4 掃 除
9—6—5 片づけ、整理
9—6—6 ごみ出し
9—7 その人にとって意味のある生活行為
9—8 役割活動の援助
9—9 対人関係を構築する援助
9—10 余暇活動に対する援助
9—10—1 レクリエーション
9—10—2 趣味活動
9—11 環境調整
9—11—1 普段の生活
9—11—2 建築環境の指針
9—11—3 看護覚え書
9—11—4 作業療法と環境調整
第10章 作業療法は参加に向かって
10—1 ICFと活動・参加
10—1—1 生活行為と参加の関係
10—1—2 つながりを見出す
10—2 コロナ禍を経験後の参加
10—3 人とのつながりから参加へ
10—4 地域の交流の場つくり
10—4—1 認知症にやさしい図書館
10—5 認知症のある人の有償ボランティア
10—6 楽しみがつくりだす仲間
第11章 家族に対する支援
11—1 家族支援と日本の動向
11—2 家族のおかれている状況
11—2—1 介護者の多様化と孤立化
11—2—2 高齢者のみ世帯の増加
11—2—3 家族が医療や福祉と出会うまでの期間
11—3 家族の心理
11—4 家族支援の目標
11—5 家族支援の具体的内容
11—5—1 作業療法士による家族を対象とした支援
11—5—2 家族の歴史を考慮
11—5—3 家族を作業療法士が支援する
11—6 家族をとりまく支援①―一体的支援プログラム
11—7 家族をとりまく支援②―さまざまな支援体制
11—7—1 認知症カフェ
11—7—2 認知症家族交流会(家族教室)
11—7—3 地域包括支援センター
11—7—4 認知症初期集中支援チーム
11—7—5 認知症地域支援推進員
11—7—6 認知症介護経験者による電話相談
11—7—7 認知症の人と家族の会
11—7—8 男性介護者と支援者との全国ネットワーク
11—7—9 レビー小体型認知症サポートネットワーク
書評
「その人らしさ」を見出す作業療法 ― 認知症支援の実践と可能性
評者:菅沼一平(京都橘大学,作業療法士)
「その人らしさを見出す」―本書の冒頭で述べられているこの言葉は、作業療法の本質を端的に表している。本書で支援事例として紹介されている血管性認知症のVさんは、転倒後の治療的安静をきっかけに朝食をつくらなくなり、食欲も低下していた。デイサービスでも活気を失っていたが、作業療法士は、Vさんがデイサービスの食事から少量のご飯を持ち帰り、20 年前に亡くなった夫の仏壇に供えていることに気づいた。Vさんは、転倒後に自力で炊飯ができなくなっても「ご飯を供える」という作業は何とか続けようとしていた。
生活機能障害(あるいは認知機能障害)が進んでも、Vさんのように、大切な人への愛情を表す行動の中に「その人らしさ」を垣間見ることができる。「趣味は▽▽である」、「○○が得意である」、「仕事は□□をしていた」というのも「その人らしさ」の一部ではあるが、たとえ、それができなくなったとしても、「誰か(あるいは自分)のために何かをしよう」という気持ちが言葉や行動に表れることこそが、「その人らしさ」ではないかと思う。言語化できない内面からにじみ出る所作にも目を向け、「その人らしさ」を見出し、作業療法士は支援の糸口を探る。Vさんに話を戻すと、作業療法士は、「朝の炊飯ができればVさんの元気も戻るのではないか」と考え、炊飯器のスイッチ横に「△△さん(夫の名前)に、ご飯を供える」という貼り紙をした。その後、Vさんはホームヘルパーの手を借りながら、炊飯器のスイッチを押す作業が習慣化され、炊きあがったご飯を仏壇に供えたあとに、自身の朝食もとるようになった。
本書は、Vさん以外にも、認知症のある人々に対する作業療法について、多くの事例を紹介している。その中で、もう一つの重要なポイントは、「認知症のある人の残存能力は、周囲との関係性の中で発揮される」という点である。認知症のある人は周囲の環境から影響を受けやすく、心理面も動揺しやすい。本書では「認知症のある人が、周囲との関係性をどのように捉え、どのような世界に生きているのか」という認知症の人の内側からみた視点を多角的に解釈しており、適切かつ具体的な環境調整の方法を示している。また、介入に至る道筋や根拠も明確で示唆に富む内容となっている。近年は、認知症のある「人」を理解し、行動・心理症状の背景や環境要因をひもとき、適切なケアや治療につなげていくことが重要視されている。本書は、作業療法の技術を生かしたアプローチを通じて、この課題に対する一つの手がかりを提示している。
事例だけではなく、高齢期の特性、認知症の疾患特性、評価尺度の紹介、観察のポイントも網羅している。これらの内容は先行研究や文献を精査したうえで整理されており、事例と照らし合わせながら医学的な知識を深められる構成となっている点も本書の魅力である。加えて、家族支援における課題にも言及し、家族介護者が直面する負担や葛藤に対する理解を深める内容が含まれている。作業療法士だけでなく、介護や医療、福祉に携わる幅広い職種の人々にとっても、重要な示唆を得ることができる一冊であり、支援者自身のかかわり方を見直し、認知症のある人の尊厳を守るための方法を学ぶうえでも、有益な書籍である。
「作業療法ジャーナル」vol.59 no.4(2025年4月号)(三輪書店)より転載
評者:菅沼一平(京都橘大学,作業療法士)
「その人らしさを見出す」―本書の冒頭で述べられているこの言葉は、作業療法の本質を端的に表している。本書で支援事例として紹介されている血管性認知症のVさんは、転倒後の治療的安静をきっかけに朝食をつくらなくなり、食欲も低下していた。デイサービスでも活気を失っていたが、作業療法士は、Vさんがデイサービスの食事から少量のご飯を持ち帰り、20 年前に亡くなった夫の仏壇に供えていることに気づいた。Vさんは、転倒後に自力で炊飯ができなくなっても「ご飯を供える」という作業は何とか続けようとしていた。
生活機能障害(あるいは認知機能障害)が進んでも、Vさんのように、大切な人への愛情を表す行動の中に「その人らしさ」を垣間見ることができる。「趣味は▽▽である」、「○○が得意である」、「仕事は□□をしていた」というのも「その人らしさ」の一部ではあるが、たとえ、それができなくなったとしても、「誰か(あるいは自分)のために何かをしよう」という気持ちが言葉や行動に表れることこそが、「その人らしさ」ではないかと思う。言語化できない内面からにじみ出る所作にも目を向け、「その人らしさ」を見出し、作業療法士は支援の糸口を探る。Vさんに話を戻すと、作業療法士は、「朝の炊飯ができればVさんの元気も戻るのではないか」と考え、炊飯器のスイッチ横に「△△さん(夫の名前)に、ご飯を供える」という貼り紙をした。その後、Vさんはホームヘルパーの手を借りながら、炊飯器のスイッチを押す作業が習慣化され、炊きあがったご飯を仏壇に供えたあとに、自身の朝食もとるようになった。
本書は、Vさん以外にも、認知症のある人々に対する作業療法について、多くの事例を紹介している。その中で、もう一つの重要なポイントは、「認知症のある人の残存能力は、周囲との関係性の中で発揮される」という点である。認知症のある人は周囲の環境から影響を受けやすく、心理面も動揺しやすい。本書では「認知症のある人が、周囲との関係性をどのように捉え、どのような世界に生きているのか」という認知症の人の内側からみた視点を多角的に解釈しており、適切かつ具体的な環境調整の方法を示している。また、介入に至る道筋や根拠も明確で示唆に富む内容となっている。近年は、認知症のある「人」を理解し、行動・心理症状の背景や環境要因をひもとき、適切なケアや治療につなげていくことが重要視されている。本書は、作業療法の技術を生かしたアプローチを通じて、この課題に対する一つの手がかりを提示している。
事例だけではなく、高齢期の特性、認知症の疾患特性、評価尺度の紹介、観察のポイントも網羅している。これらの内容は先行研究や文献を精査したうえで整理されており、事例と照らし合わせながら医学的な知識を深められる構成となっている点も本書の魅力である。加えて、家族支援における課題にも言及し、家族介護者が直面する負担や葛藤に対する理解を深める内容が含まれている。作業療法士だけでなく、介護や医療、福祉に携わる幅広い職種の人々にとっても、重要な示唆を得ることができる一冊であり、支援者自身のかかわり方を見直し、認知症のある人の尊厳を守るための方法を学ぶうえでも、有益な書籍である。
「作業療法ジャーナル」vol.59 no.4(2025年4月号)(三輪書店)より転載


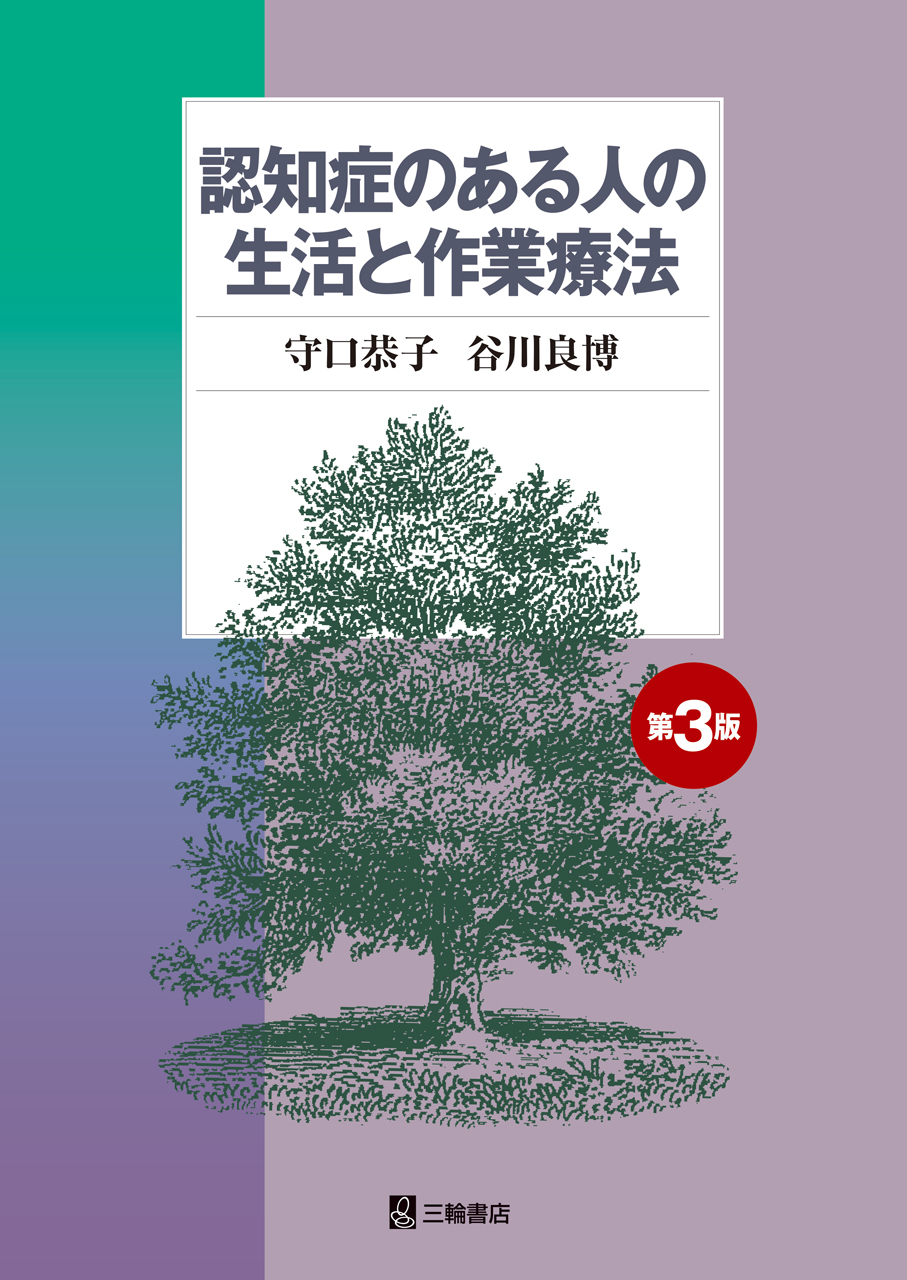
【著】
守口恭子(健康科学大学名誉教授)
谷川良博(令和健康科学大学リハビリテーション学部准教授)
※第3版ではタイトルの一部を改題しています。